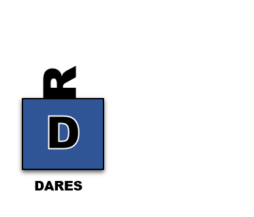相続法改正についての最後は遺産分割・遺留分・相続の効力の見直し箇所についてまとめてみます。
Ⅰ.遺産分割の効力(令和1年7月1日施行)
遺産分割前に処分された被相続人の遺産について、相続人全員の同意または処分した相続人以外の他の相続人の同意がある場合においては、遺産分割時に存在するものとみなすことができるようになりました。
これは、例えば被相続人X、相続人A、B、Cとするケースにおいて、Aが遺産分割をする前にXの預金を勝手に引き出し自分のために消費していた場合、A、B、Cの間で遺産分割協議を行うにあたって、A及びBの同意があれば、Cが消費した金銭を遺産分割の対象とすることができることを意味します。
現行法でも明文化はされてはいないものの、相続人全員の同意があれば遺産分割の対象にすることができるものと解されていましたが、先の例に当てはめるとA、BはもとよりCの同意も必要だったということが改正法との大きな違いです。
Ⅱ.遺留分の効力(令和1年7月1日施行)
まず、遺留分とは法定相続人が、被相続人の財産を最低限取得することができる権利です(相続人が直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません)。
例えば、被相続人X、相続人として妻Aと子B、Cの相続関係であった場合、Xが全財産(不動産のみとします)をCに相続させる旨の遺言を残していたとすると、A及びBは遺留分に基づきAは法定相続分の2分の1である4分の1を、Bは法定相続分の2分の1である8分の1を遺留分として、Cに請求することができます。この権利を、遺留分減殺請求権(改正後は遺留分侵害額請求権)といいます。
(1)遺留分侵害額返還請求された場合は金銭にて返還
現行法では上記の例でA及びBが遺留分減殺請求をCに対して行った場合は、Cは遺留分に相当する現物(不動産の持分)か金銭のどちらかで返還すれば良かったのですが、改正法では金銭での返還に限定されました。
現行法下では、Cは遺留分に相当する不動産の持分(物)をA及びBに返還することができましたが、改正法後は遺留分に相当する金銭で返還をしなければならないので、Cに返還するための資金が無ければ非常に困ったことになってしまいます。
ただ、それに対応する措置として裁判所に申し立てをすることにより支払猶予をしてもらえる制度も併せて創設されています。
(2)生前贈与分の持ち戻しについて
遺留分の計算をするにあたっては、相続開始時に実際に存在している財産のほかに、被相続人が生前贈与したものも含まれます。
現行法では相続人以外の者に対して行った生前贈与は相続開始時の1年前までのものを、相続人に対して行った生前贈与は無制限で遡り相続財産として計算する必要がありました。(これを持ち戻しと言います。)
改正法では、相続人に対して行った生前贈与の持ち戻し対象は相続開始前の10年以内に行ったものに限られるようになりました。
なお、持ち戻しは、①相続人全員の同意がある場合、または、②被相続人が持ち戻しを免除する旨の意思表示をしていた場合は、遺留分を侵害しない範囲で持ち戻しの免除、つまり、相続財産として計算しなくてよいことは現行法と改正後で変わりません。
改正法では上記以外にも、次の要件をいずれも満たしている場合は、被相続人に持ち戻し免除の意思表示があったものとみなすとされました。
●婚姻期間20年以上の配偶者に対してされた贈与・遺贈であること
+
●居住の用に供される建物またはその敷地を贈与・遺贈したこと
Ⅲ.相続の効力(令和1年7月1日施行)
法定相続分より多くの財産を相続した者は、その法定相続分を超える部分については登記・登録がすることができるものについては、登記・登録をしなければ善意の第三者に対抗することができないとされました。
具体的には、被相続人X、相続人A、B(法定相続割合2分の1ずつ)の相続関係で、Xの遺言でX所有の不動産はBが全て相続するとされていた場合に、Bがその旨の登記をする前に、Aが2分の1ずつの法定相続割合でA及びB名義の相続登記を行い、Aが登記を受けた持分2分の1を遺言の内容を知らない第三者Cに売却しCが登記を受けたとします。
現行法であれば、登記より遺言の効力の方が優先されるため、Cが登記を受けていたとしても、BはAが売却した持分は無効としてCが取得した持分を取り返すことができました。
しかし、改正法では、登記が第三者対抗要件とされたことから、Cが善意の第三者(Cが持分2分の1をAが相続していないことを知らなかったということ)であれば、Cが先に登記を受けた以上、BはCに対してその売却が無効であることを主張できなくなります。
相続登記は、法定相続の割合であれば一人の相続人から登記申請を行うことができるため、決してありえないことではないと思います。ですのでこのような遺言で不動産を取得した相続人の方は速やかに相続登記を行った方がいいでしょう。
横須賀の司法書士 DARES(ダレス)司法書士事務所